2015年秋の第10問は新QC七つ道具について。今度は新だそうですよ。ツール関係の問題が大半だね。よく覚えなくちゃ。おいちゃんは覚えるのが苦手なんだ。
概要
QC七つ道具が数値データの解析用であったのに対し、新QC七つ道具は言語データを図形化・視覚化することで整理する方法だそうです。テキストを読んで大きく3つに分けることができそうだったので、今回を含めて3回に分けてお届けしますよ。(分類はおいちゃん感覚)
第1回目は事象の整理と関連付けをおこなうと思われる手法の親和図法、連関図法、系統図法についてです。
親和図法
親和図法とは解決すべき問題の姿を明らかにし、アイデア・発想の着眼点を得ることができる手法です。
やり方としてはある目的で収集された言語データを簡潔な表現でカード化し、意味が似ているカードを集めてグループ化して整理します。このとき図形化されたものが親和図になります。
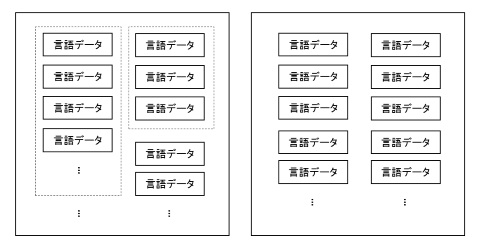
これを使うことで混沌としている事象を整理し、問題を明確に浮かび上がらせることができます。漠然とした問題について、事実・推定・予測・発想・意見を言語データで捉え、相互の親和性によって統合した図を作ることで、何が問題か?どのような問題か?が明らかになります。
連関図法
連関図法は問題解決のために因果関係を論理的に繋ぐことができる手法です。
関連じゃないよ。れ・ん・か・ん。
やり方としては問題点を中心に1次要因、2次要因と矢線で繋いで広げていって、「なぜなぜ」を繰り返しながら因果関係の繋がりを示します。このとき図形化されたものが連関図になります。
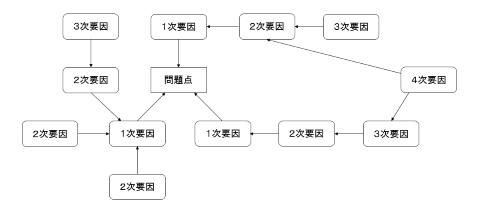
特性要因図に似てるんですが、要因図が要因を洗い出して根本原因を探るのに対し、連関図は複雑な原因が絡み合うような問題を扱うのに適しているようです。特性要因図同様に要因のレベルを動かして結果の変化を調べるなど、仮説の検証が必要になります。
系統図法
系統図法は問題を効果的に解消するために最適手段を系統的に展開する手法です。
やり方は目的を達成するための手段・方策を1次、2次と系統的に展開してゆきます。このとき図形化されたものが系統図になります。
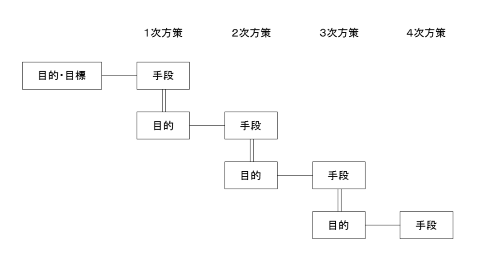
事象→問題→原因→対策と系統的に展開して、最適な手段を探ります。なお、対策案の整理・検討においては
- 効果の大きさ
- 必要な費用
- 難易度
- 期間
- 他工程への影響
などを評価して採否や優先順位を決めるようにします。